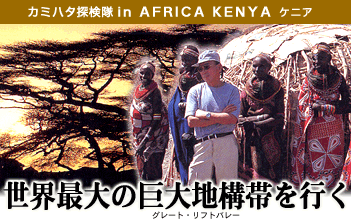
text & photo/神畑重三 協力/神畑養魚(株)
+++ Vol.1 +++
| 「世界最大の巨大地構帯(グレート・リフトバレー)を行く」
日本の湖とは比較にならない、サバンナの湖。太古はナイル河の一部であった“翡翠の海”トゥルカナ湖、琵琶湖の100倍もの大きさのビクトリア湖。果たしてどんな魚に、人々に出会えるのか・・・。 |
清涼な面影をなくしたナイロビ
 |
| ■眼下のサバンナにキリマンジャロが見えてくる |
ジャンボ・ジェットの最新鋭機がゆっくり機体を揺らしながら、南アフリカのヨハネスバーグ空港に着陸した。夜明け前の東の空は茜色に染まって美しい。明けやらぬ早朝の空港はまだ薄暗く、人影はまばらだが、きびきび働く黒人の姿がひときわ目立つ。以前と違って、彼らののびのびとした表情がまことに印象的だ。
3年前、マラウィへ向かう途中、この空港に立ち寄ったことがあったが、そのころはマンデラ氏を中心とする黒人主導の政権が誕生する直前であった。長かった白人による黒人差別のアパルトヘイト政策が消滅する直前の政情不安のさなか、空港ロビーは1週間前にテロリストによって爆弾が投げ込まれ、多数の死傷者を出したばかりで、警備は厳重を極め、ぴりぴりと緊迫した空気に包まれていた。
空港内のVIPラウンジで熱いシャワーを浴びると、長旅の疲れがいっぺんにふっ飛んでしまった。ここからケニアのナイロビまで4時間少々のフライトだ。薄紫色の靄にうっすらとかすむ赤褐色のサバンナの上空を順調に飛び続けて、昼すぎにジョモケニヤッタ空港に降り立った。日本からこの空港までの正味の飛行時間が24時間かかっている。アフリカはやはり遠い。
友人のビンセントが空港の送迎デッキで盛んに手を振っている姿がすぐに目に入った。彼はアフリカ人の中でもひときわ背が高いので、すぐに見分けがつく。6年前、この地を初めて訪れたとき、ガイドとして雇ったのが彼との出会いであった。われわれがサバンナの水溜りで魚をとったり、水草を採集するのに興味を持って、そんなことが仕事になるのなら、ぜひ自分もやってみたいというので、その翌年にドイツで開催されたインターズー(世界最大のペットショー)に招待してあげて以来のお付合いである。
彼は自分の部族のために適当な仕事を探していたが、アフリカ産のリクガメ養殖の共同開発を思いつき、いろいろな障害を乗り越えて、やっと許可が降り、昨年末に日本への輸出を始めたばかりである。今回の旅行目的の1つは、リクガメの養殖場建設の実状や政府機関の関係者との今後の計画についての打合せである。同行するのは、当社の小笹と、友人のシンガポールのヨーである。
久しぶりに訪れたナイロビ市内はすっかり変貌していた。町にはやたら車が増えて、交差点に信号がほとんどないため、慢性的な交通渋滞になる。整備の悪い車が出す排気ガスと騒音がすさまじい。乾期ということもあいまって、からからに乾燥した道からはゴミや埃が舞い上がり、汗まみれの肌にべとべとまとわりつく。
ナイロビは、スワヒリ語で「冷たい水が湧くところ」という意味だそうで、標高1700mの高地に位置するこの地は、以前はアフリカの軽井沢とも言われる納涼地であったが、今は清涼とした面影がまったく感じられない。
当地唯一の魚のシッパーであるマニーのストック場の見学に向かったが、町中はまるでスモッグと埃のトンネルだ。しかも、ところ構わず車が強引に割り込んでくるので、危なくてはらはらどきどきするなか、やっとの思いで郊外に抜けると、そこはおぞましいほど貧しいスラム街が展開されていた。ヨーが「これほどのスラム街は東南アジアにはない」と興奮して、車から身を乗り出してビデオを撮ろうとすると、ビンセントに「危険だからやめろ」と注意されていた。
ケニア人の平均的な月収は、日本円で5000円ほどだが、食料品は安く、肉は1kgで200~300円ほどだ。しかし、庶民の生活は楽ではない。
キマニーのストック場は水槽の数が30本ほどで、濾過装置のない粗末なものだったが、魚の調子は悪くない。ナイル・パーチ、ドワーフ・エジプシャン・マウスブリーダー、肺魚など、ロンドン向けの出荷直前の魚が用意されていた。
サバイバル法の異なる2種のリクガメ
リクガメの養殖場を訪問するため、交通渋滞を避けて早朝にホテルを出た。市内の雑踏を抜けて郊外に出ると、車も人も少なくなり、道の両側には、紅茶畑、ラクダの牧場、デルモンテのプランテーション、パピルスの自然群生地などが見られる。
ビンセントによると、ケニアは50余りの部族から構成されている国だそうで、言葉はスワヒリ語を基本としているが、部族ごとに少しずつ異なるという。しかし、これだけ部族が多いと、かえって争い事が少なく、平和が保たれるらしい。その反対が隣国のルワンダで、おもにツチ族とフツ族の2つだけで構成されているため、部族間の闘争と殺戮はすさまじく、このニュースが世界の人々に与えた衝撃はまだわれわれの記憶に新しい。
これと同じことが魚の世界にも共通するようで興味深い。たとえば、1つの水槽にアロワナを2、3尾だけ入れた場合、ぼろぼろになるまで戦うが、数をたくさん入れると争わず、比較的平和が保たれる。魚も人間も似たようなことをやっている。
ムウィンギという町の質素なバラック建てのケニア野生動物サービスのオフィスに到着した。この国はアフリカでも動物保護の規制と監視の厳しいことで定評があり、われわれのリクガメ養殖場はその管理下にある。
 |
| ■旅人の木と呼ばれるバオバブ |
道は舗装道路から赤土に変わってサバンナらしくなってきた。道の両側には2抱えも3抱えもありそうな大きなバオバブの木が天高くそびえている。アフリカを象徴するこの木は、太い幹に細い小枝と申し訳程度の葉がついているだけで、その奇怪な姿は魚の寄生虫のイカリムシそっくりだ。木の幹に耳をあてがうと、かすかに水の流れる音がするという。この木は“旅人の木”とも呼ばれているが、木に含まれる水分がサバンナを行く旅人の渇きを癒して人助けすることからその名の由来がある。
ナイロビから200数十km走ってリクガメ・ファームのあるガニ村に到着した。“ガニ”とはカメという意味だそうだが、この地方の気候と土質がカメの生息に適していて、この周辺には1万頭からの野生のリクガメが生息しているという。
ファームには自然の雑木林と、その後方に亀裂の入った高さ30mの岩山があり、これをフェンスでぐるり取り囲んで、その内側に手造りのブロックを積み重ねてカメの逃亡を防いでいる。木陰のところどころにカメのための水浴プールが設けてある。日中が暑すぎるせいで、ほとんどのカメは石垣の間や木株の割れ目に入って直射日光からの猛暑を避けている。しかし、気温の低い早朝はカメがよく動き回り、餌を求めて出てくるのだそうだ。餌はおもに野菜や果物を与えているが、カルシウムやリンの不足を補うため栄養剤が振りかけられていた。
レオパードの親ガメは甲羅が直径50cmもあり、背中が鉄兜のように盛り上がり、自分の体重を持ち上げるのに苦労するほど重そうだ。また、パンケーキ・リクガメはからだは柔らかく、親でも15cmほどしかない。たいていのカメは固い甲羅で外的から身を守っているが、敵に襲われるとパンケーキは岩の割れ目に逃げ込む習性を持っているという。甲羅が柔らかくて平ベったいため、岩の奥まで入り込めるわけだ。それでもなお危なければ、からだを風船のように膨らませて、引っ張り出されるのを防ぐとのことだ。同じ場所に棲む2種類のカメが生存のために極端に違うサバイバル法を身につけている点は、なかなかに興味深い。
 |
 |
 |
| ■レオパード(ヒョウモン・リクガメ)は鉄かぶとのように固い甲羅で身を守る | ■パンケーキ・リクガメは甲羅が柔らかい。この特性で身を守るのだ | ■カメは昼間は暑さを避けるため、木陰に寄り添う |
カメの最大の天敵はサバンナ・アリで、雨期に入るとサバンナから出てきたアリの大群がカメを襲い、まず目を攻撃して、動けなくなったカメに群がって食べ尽くすという。大山猫も天敵の1つで、これを防ぐには周囲に高いフェンスを張り巡らせるしかない。小銃を手にした警備員を見受けたが、生き物の養殖には人知れない苦労が伴うものだ。
 |
| ■カメのファームの飼育係 |
後方の岩の上は200坪ほどの台地になっていて、その真ん中にバオバブの大木があり、それを取り囲むように数家族が茅葺き小屋に住んでここを管理している。高床式で風通しがよく、ひんやりした木陰は眠気を誘うほど気持がいい。カメ・プロジェクトのスタッフであるサンブラ氏は元ケニア博物館の館員で、魚とカメに経験の深い彼がチームの一員に入っているので心強い。カメの専門用語を使った彼の話は私にはちと難しすぎるが、英会話があまり得意でないのに、小笹がそれを理解して私に説明してくれる。さすがに専門の大学院を卒業しただけのことはある。
「絶滅に瀕した動物を保護して後世に残すには、人工的に養殖させることがそれを救う唯一の方法で、規制だけしても密輸が増えるだけで意味がない」という私の持論にケニア・ワイルド・サービスが同意してくれ、ささやかながらアフリカの大地にリクガメ養殖の試験的なファームの第一歩を踏み出せたことがとにかく嬉しい。同時に、このファームが産業を持たないサバンナに住む人々の糧を稼ぎ出す手段になっていることは二重の喜びであった。
